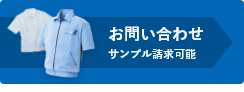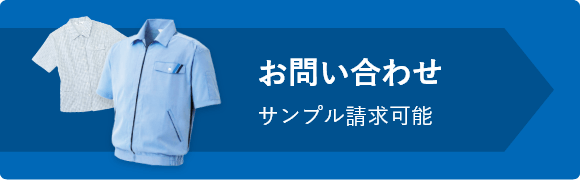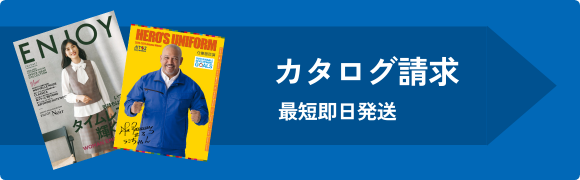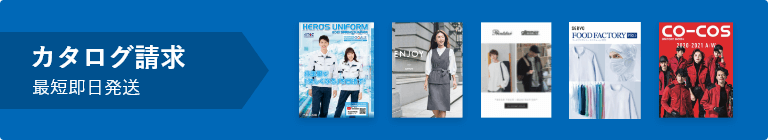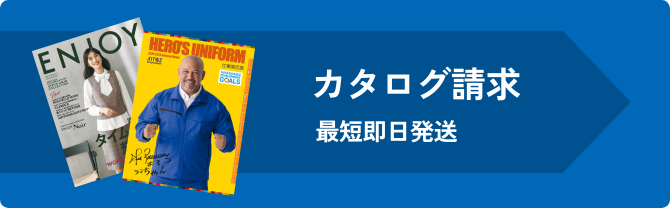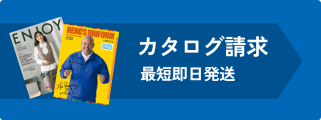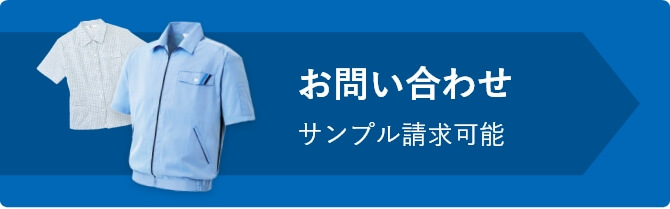作業着のお直しはどうしたらいい?必要になるケースもご紹介
作業着を毎日着用するお仕事をされている方にとって、作業着のお直しは避けては通れない問題です。「作業着のポケットが破れたけど、どうやって直したらいいんだろう」「体型が変わって作業着がきつくなってしまった」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
作業着のお直しには、いくつかの選択肢があります。この記事では、作業着のお直しが必要になるケースや、お直しの種類、自分でできる簡単な直し方までを詳しく解説していきます。
作業着を日常的に使用する方にとって、お直しの知識は作業効率や安全性、経済的な面でも重要なポイントとなります。
作業着のお直しとは

作業着のお直しとは、業務中の動きやすさと安全性を維持するために行う、破れや劣化した部分の修繕作業のことです。
お直しには主に二つの方法があります。一つ目は専門業者に依頼する方法で、高品質な仕上がりが期待できるものの、費用がかかるデメリットがあります。特に耐久性が求められる部分や複雑な修繕は、プロの技術が安心です。
二つ目は自分で行う方法で、簡単な裾上げやボタン付けなどの軽微な修繕に向いています。費用を抑えられる反面、仕上がりの品質は技術によって左右されてしまいます。
作業着のお直しを行うタイミングも重要なポイントです。生地の擦れや薄くなりが目立ち始めたら、破れる前に対処するのがおすすめです。特にひじや膝、ポケット周りは負荷がかかりやすく、早めの対応が必要になることが多いでしょう。
また、作業着の素材によってお直し方法が異なるため、綿、ポリエステル、混紡など、素材の特性に合わせた修繕方法を選ぶことが大切です。
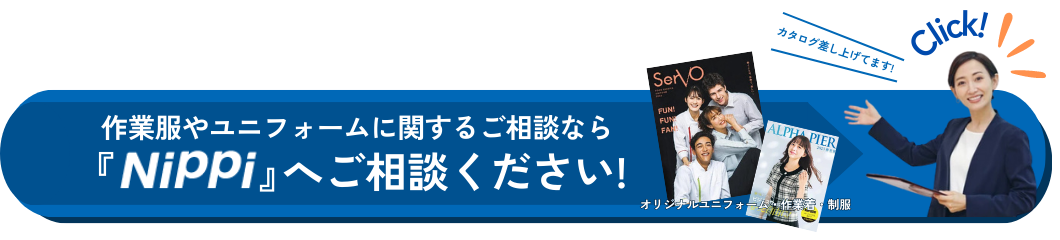
作業着のお直しが必要になるケース
作業着のお直しが必要になるケースは多岐にわたります。長期間の使用による生地の破れや摩耗、体型変化によるサイズ調整、会社のロゴやネーム変更など、作業着を新調する前に一度お直しを検討してみましょう。
適切なタイミングでのメンテナンスは作業着の寿命を延ばし、経済的にも賢い選択になります。
破れや生地の損傷
作業着を毎日使用していると、さまざまな理由で破れや生地の損傷が発生します。まずは早めの対処が重要です。破れや損傷を放置すると、小さな傷が大きくなり、最終的には修復不可能になってしまう可能性があるからです。
破れが発生しやすい箇所には特徴があります。膝や肘などの関節部分、ポケット周り、股下や脇の縫い目部分が代表的です。これらの部分は動作によって常に負荷がかかるため、他の部分より早く劣化する傾向にあるのです。
特に頻繁に物を出し入れするポケットは、破れやすい部位として注意が必要です。
結局のところ、作業着の破れや生地の損傷は、安全性や見た目だけでなく、仕事の効率にも影響します。小さな損傷を見つけたら、すぐに適切な修繕方法を検討することが作業着を長持ちさせるコツなのです。
サイズ調整が必要な時
体型の変化や職場環境の変化により、作業着のサイズ調整が必要になることがあります。適切なサイズの作業着は、作業効率を高め、安全性を確保する重要な要素なのです。
作業着がきつすぎると動きが制限され、ゆるすぎると機械への巻き込まれリスクが高まります。特に建設業や製造業では、体にフィットした作業着の着用が安全管理の基本となっています。また、長時間の作業では不適切なサイズによる体への負担も無視できません。
企業ロゴやネーム変更
企業の制服やユニフォームとして使用される作業着は、会社のロゴやネームプレートの変更が必要になることがあります。これは会社のブランドイメージ刷新や組織再編、部署異動などに伴って生じる重要な変更点なのです。
実際の対応方法としては、古いロゴの上から新しいロゴを縫い付けるオーバーレイ工法が一般的です。また、既存のロゴやネームを丁寧に解いて取り外し、新しいものを付け直す方法も よく採用されています。大量の作業着を一度に修正する必要がある場合は、専門の作業着お直し業者に依頼するとスムーズに進むでしょう。
作業着のお直し種類
作業着のお直しには様々な種類があり、お困りごとに合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。破れや摩耗した部分の修繕、生地の補強、ポケットの付け替えなど、作業着の状態や損傷の程度によって対応方法が変わってきます。
裾上げ・丈詰め
作業着の裾上げ・丈詰めは、一般的で需要の高いお直し方法です。作業中の安全性と動きやすさを確保するために、適切な長さに調整することが重要なポイントとなります。
作業着の裾が長すぎると、つまずきや機械への巻き込みなどの危険性が高まってしまいます。特に工場や建設現場では、安全面のリスクを減らすために裾上げは欠かせません。
また、見た目の美しさや清潔感を保つためにも、適切な丈に調整することが大切です。
裾上げを依頼する際は、洗濯による縮みも考慮して少し長めに調整してもらうと安心です。また、作業着は一般的な洋服よりも頑丈な素材が使われているため、専門的な知識と設備を持つ業者に依頼すると、美しく丈夫な仕上がりになりますね。
補強
作業着の損傷には、目立たないようで実は重要な「補強」という選択肢があります。これは既に弱っている部分を事前に強化することで、破れを未然に防ぐ賢い方法なのです。
補強は特に摩擦や負荷が繰り返しかかる部分に効果的です。膝や肘、ポケットの縁など、日常的に負担がかかる箇所に丈夫な生地やパッチを追加することで、作業着の寿命を大幅に延ばすことができます。
予防的な補強は、完全に破れてからの修理より見栄えも良く、コスト効率も高いメリットがあります。
サイズ調整
作業着のサイズ調整は、快適な作業環境を維持するために欠かせない重要なお直しです。体型変化や季節による衣服の重ね着、業務内容の変更などで合わなくなった作業着も、適切な調整で再び活用できるようになります。
実際のサイズ調整では、着用する人の動きに合わせた工夫が必要です。例えば、腕を頻繁に上げる作業なら肩回りに余裕を持たせる、しゃがむ動作が多い職種なら膝周りの可動域を確保するといった配慮が大切になってきます。
特に安全に関わる作業着は、余分なたるみがないよう調整することで、機械への巻き込み事故も防止できるのです。
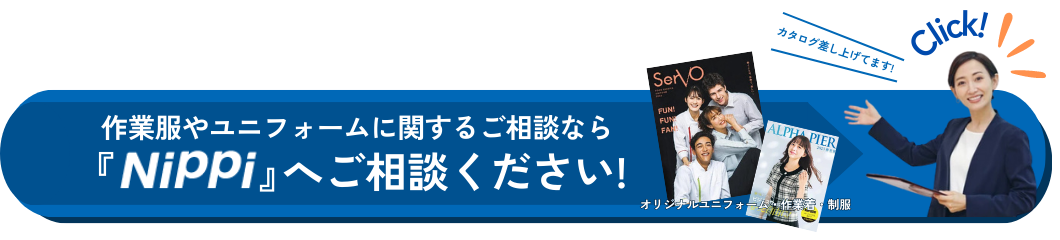
自分でできる簡単な作業着のお直し方法

専門店に依頼するほどではない簡単な作業着のお直しなら、ご自宅でも十分対応できることがあります。裾上げテープやミシンを使った基本的な修繕方法を身につけておくと、急な破れや細かな調整にもすぐに対応できるので便利でしょう。
裾上げテープを使用する
裾上げテープを使うと、ミシンや手縫いの技術がなくても簡単に作業着の裾上げができます。特に急ぎの修繕や一時的な対応に最適なアイテムで、初心者でも失敗の心配なく使えるのが魅力です。
裾上げテープを選ぶ際は、作業着の素材に合ったものを選ぶことが大切です。綿素材の作業着には綿用、化学繊維には合成繊維用と、素材別に専用のテープが販売されています。間違ったテープを使うと接着力が弱かったり、洗濯で剥がれやすくなったりするので注意が必要です。
使い方は簡単で、まず作業着のズボンを希望の長さに折り、アイロン台の上でしっかり折り目をつけます。次に折り目の内側に裾上げテープを挟み込み、説明書通りの温度・時間でアイロンを当てれば完了です。
ただし、裾上げテープでのお直しは永久的な解決策ではありません。頻繁に洗濯する作業着の場合、徐々に接着力が弱まることがあるため、重要な場面前には状態をチェックしておくと安心です。
ミシンを使って直す
ミシンを使えば、作業着のお直しがより丈夫で見栄えの良い仕上がりになります。
まず準備するものは、ミシン本体、作業着の生地に合った糸、針、はさみ、まち針です。作業着は通常丈夫な生地でできているため、11号〜14号の少し太めの針を選ぶと良いでしょう。
破れを修繕する場合は、まず破れの周囲をきれいに整え、裏側から補強用の当て布をあてます。当て布は作業着と同じか、それより丈夫な素材を選ぶのがポイントです。まち針で固定したら、ジグザグ縫いで破れの周囲を縫い付けていきましょう。
まとめ
作業着は日々の仕事で酷使されるものですから、破れや生地の損傷、サイズの不具合、企業ロゴの変更などにより、お直しが必要になることがよくあります。
お直しの方法には、裾上げや丈詰め、ポケットの修理、サイズ調整など多様な種類があり、状況に応じて最適な対応を選ぶことが大切です。専門店や仕立て屋に依頼する方法もありますが、裾上げテープやミシンを使った簡単なお直しなら、自分で対応することも可能ですね。
作業着を適切にお直しすることで、買い替えのコストを抑えられるだけでなく、環境にも優しい選択になります。また、きちんと体にフィットした作業着は、作業効率の向上や安全性の確保にもつながります。
 カタログ一覧
カタログ一覧